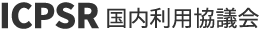2024年度 体験談01
| 参加年度 | 2024年 |
| 所属 | 同志社大学 法学研究科 |
| 課程 | 博士課程 |
| 参加形式 | 現地参加 |
Summer programに参加されたきっかけを教えてください。
指導教授の先生、さらにその先生の指導教授であった先生がそれぞれ大学院生時代に受講していたことから、指導教授の先生に勧められたことがきっかけ。元々昨年度(M2)参加するつもりでいたが、自身の英語力や統計学の理解度を高めてから参加しようと、今年度の参加となった。参加目的は、2つ。一つ目に世界最先端の授業を受けることで自身の計量分析スキルを高め、統計学への理論的な理解も高めること。二つ目に、アメリカでのキャンパスライフを体験すること。日本での博士課程生活を送る私にとって貴重な経験。今後指導する学生が海外留学を考えた時に、多少なりとも話ができると考えた。
受講したセッション、コース名を教えてください。
「Matrix Algebra, Calculus, and Probability: Introduction and Review
Introduction to Python
Data Science and Text Analysis
Causal Inference for the Social Sciences II
Categorical Data Analysis: Models for Categorical, Ordinal, and Count Outcomes」
期間は7/8〜8/2の4週間。最初の一週間で数学や統計言語の基本的なレクチャーが行われる。渡米前にシラバスを読込み受講するレクチャーを決めたが、初日の説明会でドロップしない限り、全ての受講者が全てのレクチャーに登録され、オンラインシステムのcanvasから授業資料や講義動画にアクセスできることが説明された。私はR言語についてはある程度慣れていた為、午前中に数学(行列代数、微積分、確率)を4時間(またはビデオで後日)、午後にpythonを4時間受講した。
二週目〜四週目はメインの授業である、コースセッションが開かれる。二週目の月曜日にphoto sessionの後、担当者から改めて各講義の説明がなされ、二週目の半ばまでに受講する講義の変更や追加が許される。4つまで授業を登録することができるため、私は毎日午後に開催されるcausal inferenceを対面で受講し、カテゴリカルデータ、パネルデータ、テキストアナリシスは動画で受講した。毎日午前と夜は各講義の動画視聴、復習、課題の提出にあてた。
対面で受講したcausal inferenceのカロニコ先生はコロンビア大学の先生で、RDDという手法を使う際には避けては通れないパッケージを開発した人。日本語の教科書でも必ず引かれており、因果推論を用いた計量経済学系ではおそらく知らない人はいないのでは無いかというくらいの人。
受講前の準備について、受講までの間にどのような準備を行ったか教えてください。
渡米するまでに特別な準備はしなかった。今年度行くことを決めてから1年間、週2〜3回の英会話レッスンに通ったおかげで、最低限の英会話をすることはできた。他大学の勉強会にzoomや対面で参加していたことから、受講する講義についての事前知識を得られていたり、日本語の資料をpdfで持っており、発展的かつ最新の研究を紹介する授業でもなんとかついて行くことができた。
講義内容について、授業の進め方やクラスの規模、授業の難易度について教えてください。
最初のレクチャーは基本的な内容。数学は基本的な代数をかなり熱意を込めて説明してくれた。しかし最後の二日間はとても高度な内容で完全に理解するのは難しかった。二週目からは多岐にわたる。だいたい参加者は授業によるが10〜30人ほど。zoomでそれぞれ10〜20人ほど。他は動画のみの受講のために登録している人。授業では主に理論の説明、先生が前でコードを動かして説明、その後授業によってはTAと先生によるlabセッションが開かれる。課題はA4が1〜2枚で出されて、自分でコードを動かして問題に答えていく形式である。パネルデータではどのようにして異質性を排除するのか、そのための検定やその理論的背景、分析方法の違いなどについて学んだ。2.3日に一回課題があり、かなり大変だったが、修士論文で使用していた手法だったので、動画のみの受講でもなんとかついていけた。causal inferenceは因果関係を特定するための実験手法、実験手法が使えない時のための操作変数法・差の差分析・回帰不連続デザインなどの基礎とそれぞれの手法の最先端の分析や今学説的にどこが争点になっているのかを学んだ。
最終週には、機械学習を用いて因果関係を特定する最新の手法について一週間を使ってみっちりと学んだ。課題は毎週末に出されて、それぞれの手法について、授業の理解度を試すような問題が12〜3問出され、Rで分析を行いその結果を解釈するようなものだった。それ以外は課題出した授業と、課題を出さずに帰国後などに改めて資料や動画を見て学んだ授業もある。12/31まで講義動画はいつでもみることができる。
プログラム期間中の学習について、予習や復習、課題の取り組み方について教えてください。
だいたい7:30くらいに起きて、朝の授業時間を使って、対面で出ていない授業の受講や復習、課題に取組むなどした。午後は毎日対面で参加。帰宅後少し散歩をしてから、また復習と課題に取り組み、毎日23:30くらいには寝ていた。
プログラム期間中の授業以外の活動について、他の参加者との交流やイベントについて教えてください。
同じ研究室の後輩(そのままミシガンに残りミシガン大学に進学したM1と一年間ミラノ大学に留学しており久々の再開だったM2)と一緒だった。初日の交流会や二週目の初日の交流会でかなり友達ができる。また、寮のラウンジなどでも話しかけて積極的に友達を作った。初日にwhat's upのグループに入れてもらったおかげで、色々な情報を手に入れられたし、飲み会や食事会、公園でスポーツの誘いなども受取ることができた。
週末には、大学内にある博物館、美術館、図書館、グッズショップ、スタジアムなどをまわったり、特色ある校舎を見学していた。一週目の週末にはデトロイトのコメリカパークに行き大谷の200号を見ることができた。二週目にはダウンタウンでアートフェスというお祭りが開催され、堪能することができた。治安はとても良く、人々は穏やかで、アジア系も多く含む多様なレストランがあり、歩いていて楽しい街だった。事前に知人から仕入れたご飯情報を頼りに食べ歩きもした。誘われて、15人くらいでスポーツバーで飲みながらeuroの決勝も見た。毎週水曜日の朝はドーナツデーで、本部にコーヒーとドーナツが置かれていて、話しながら楽しむことができた。
二週目の週末にはピクニックが催され、ご飯を食べて、キャッチボール、キックベース、バレー、バスケをしてTAさんも含めてさらに仲を深めた。野球をしていたこともあり、いいプレーができるとみんなから話しかけられて、さらに新しい友達ができた。その後車で7時間かけてきていたアメリカph.d在学中の台湾人の子たちからアジアンマーケットに誘われたので、買い出しもすることができた。 夜の飲み会は週1〜2回自然発生的に行っていた。
現地での生活について、宿泊場所の確保、食事の調達、身の回りの生活品の買い物などについて、困ったことやおすすめの情報があれば、教えてください。
住居はストックウェルホール。ジムが使い放題なので、毎週2回朝にトレーニングをしていた。食事は併設の食堂でほとんど食べていた。朝は6$、昼夜13.5$。デポジットした300$が切れると、カードでの支払いとなり、少し割高になる。昼は外でもう少し食べても良かった。基本的に毎週昼夜2〜3回ずつは外食していた。 Rich.J.CやKan'sなどの韓国料理はおススメ。
Summer program参加の感想について、印象に残ったこと、プログラムを通じて得られたこと、あなたの研究やキャリアに活かされたことがあれば、教えてください。
このプログラム参加によって、①世界最先端の手法について理解を深めた、②国際的な研究ネットワークを構築した、③(一か月ではあるが)アメリカでの学生生活の体験ができた。 今後は、①さらなる国際学会での報告、②(すでに行っているが)英語での論文執筆と投稿、③準実験的な因果推論の手法による研究の幅の拡大、をおこなっていきたい。
参加を検討されている方、参加を迷われている方にアドバイスやメッセージをお願い致します。
とにかく早くwhat’s upのグループに入れてもらう。 現地生活に早く慣れて、アナーバーの街を堪能する。 Canvasのシステムに早く慣れる。 国内利用協議会の日本語資料をアップデートしてもらったので、その資料を事前によく読みこむ。